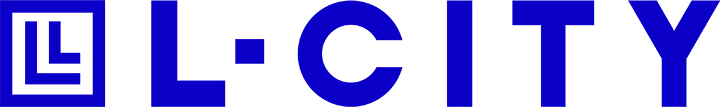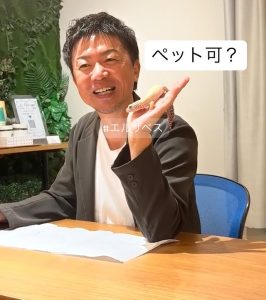不動産購入で賢く節税|減価償却・住宅ローン控除・3,000万円特別控除までやさしく解説
不動産購入は資産形成だけでなく節税対策としても有効です。本記事では、意外と知られていないポイントを中心に、減価償却・諸費用の軽減措置・住宅ローン控除・3,000万円特別控除・損益通算・相続対策まで、やさしく整理して解説します。制度は改正があり得るため、適用前に最新情報を確認しましょう。
1. 減価償却で課税所得を圧縮(不動産所得)
- 建物部分は経年劣化を前提に、耐用年数に沿って毎年減価償却費を経費計上可能。
- 目安:木造22年、RC(鉄筋コンクリート)47年など(税法上の耐用年数)。
- 現金支出がなくても経費化できるため、課税所得の圧縮に直結。
- 土地は償却不可。購入価格の按分(建物/土地)に注意。

2. 取得時の諸費用と軽減措置
- 登録免許税・不動産取得税には一定の軽減措置あり(要件充足が前提)。
- 住宅ローン控除:一定条件で所得税の税額控除(上限や適用年、対象範囲は制度改正により変動。最新要件の確認必須)。
- 取得時諸費用のうち、不動産所得の必要経費となるもの(仲介手数料の取扱い等)は用途によって異なるため整理が必要。

3. 居住用財産の3,000万円特別控除(売却時)
- 居住用財産を売却した場合、一定の条件下で譲渡益から最大3,000万円控除。
- 住み替え時の税負担を大きく軽減。適用要件・併用制限(特定居住用財産買換え等)に注意。

4. 不動産投資の損益通算で税負担を低減
- 不動産所得が赤字の場合、給与所得などと損益通算できる場合がある。
- 購入初期は金利負担が大きく、赤字が出やすい→全体の税負担を抑えやすい。
- ただし、租税特別措置や損益通算の制限が生じ得るため、最新制度を確認。

5. 相続対策:評価額の圧縮効果
- 不動産は相続税評価額が市場価格より低く算定されることが多い。
- 賃貸不動産は賃貸割合に応じて評価が下がる傾向(借家権割合等)。
- 現金から不動産への組み替えで、相続税の評価圧縮が期待できる場合あり。

6. 適用前のチェックリスト
- 最新制度の確認:控除額・適用期間・対象条件・申告方法。
- 用途の切り分け:居住用/賃貸用で取扱いが異なる項目を整理。
- 建物価格の按分:減価償却の前提となる建物割合の根拠を明確に。
- 証憑管理:契約書・請求書・領収書・登記事項証明書の保管。
- 将来の出口:売却時の特例(3,000万円控除等)まで見据えて計画。

よくある質問(FAQ)
土地と建物の按分はどう決める?
公的評価や不動産会社の内訳資料、同地域の取引事例など合理的根拠に基づいて按分します。建物割合は減価償却に直結するため、証憑の整備が重要です。
住宅ローン控除は投資用でも使える?
原則として自己居住用が対象です。投資用(賃貸用)は対象外が基本。居住要件・床面積・年収要件・適用年など、最新の法令・通達を確認してください。
損益通算はいつまで有利?
金利・減価償却・空室率などで変動します。初期は赤字でも償却の進行や返済の進捗で黒字化するケースが多く、通算の可否・範囲は制度改正に左右されます。
相続対策で不動産を買えば必ず税が下がる?
必ずしも下がるとは限りません。評価や賃貸割合、借入の有無、家族構成により効果は異なります。相続時精算課税や小規模宅地など他制度との関係も要確認です。
注意事項
本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、税務アドバイスではありません。適用可否や効果は個別事情・時点の法令で異なります。実行前に税理士・専門家へご相談のうえ、最新制度をご確認ください。